「Monaca Education」で実現する、生徒主体の探究活動/群馬県立高崎高等学校
群馬県立高崎高等学校は、高崎市にある1897年設立の伝統校です。文武両道を掲げ、県内随一の進学実績を誇ります。また、文部科学省のスーパーサイエンスハイスクール(SSH)に指定されており、令和3年度からは第Ⅳ期に突入。「Society5.0時代を牽引するリーダーとしての資質・能力を備えた人材の育成」を目標に教育活動に取り組んでいます。
探究活動における「Monaca Education」の実践的な活用を主導する、SSH部長、物理部顧問で物理担当の 岡田直之 教諭にお話を伺い、3年生 物理部 黒澤駿さんと森田大智さんに活用した感想をお聞きしました。(2025年1月インタビュー)

群馬県立高崎高等学校
探究授業の進め方、「Monaca Education」との出会い
SSHにおける3年間の探究授業の進め方を聞かせてください。
岡田教諭:1年次に3単位、2年次にはコースにより2〜3単位、3年次は1単位と「課題研究」の時間を豊富に確保しています。身の回りにある課題を解決し社会をよくすることを考えるのが探究ですが、本校では、実験などを通じて真理を追求する「学術型」、社会に役立つものを作る「開発型」、社会をより良くするアイデアを考案する「提案型」を用意しています。「開発型」における本格的なアプリや「提案型」におけるプロトタイプとしてのアプリを開発する生徒が多いのではないかと思います。

高崎高校 SSH部長、物理部顧問、物理担当 岡田直之教諭
「Monaca Education」を採用されたきっかけ、狙いを教えてください。
岡田教諭:探究で大事なことは、アイデアを形にする「作る」ということにあると思います。アイデアを出して終わりではなく、「プロトタイプを作り、世に問う」「改善する」というサイクルにこそ学びがあります。
授業で全員にそうした学びを提供しようとした時に、マイコンなどハードウェアまで扱うのは困難なので、ソフトウェア開発が良いと当初から考えました。最初はノーコード(コーディング無しで開発できるツール)も候補にしましたが、ツールが固定されてしまいますし、もう少しプログラミング要素がほしいと思い、探している中で「Monaca Education」を見つけました。
「Monaca Education」でどう学ぶ?
「Monaca Education」によるアプリ開発はどのように指導していますか?
岡田教諭:1年生の3月頃に「Monacaで学ぶアプリ制作入門」を配布し、「5月の連休明けに開発したアプリを発表してもらいます」と、いきなり進めました。ChatGPT(チャットジーピーティ)など生成AIを使って調べてもよく、自学用の情報を掲載したオリジナルポータルサイトも公開しました。それだけでは難しいので地元企業のエンジニアの方に協力をしてもらいハンズオン形式の授業も何回か実施しました。
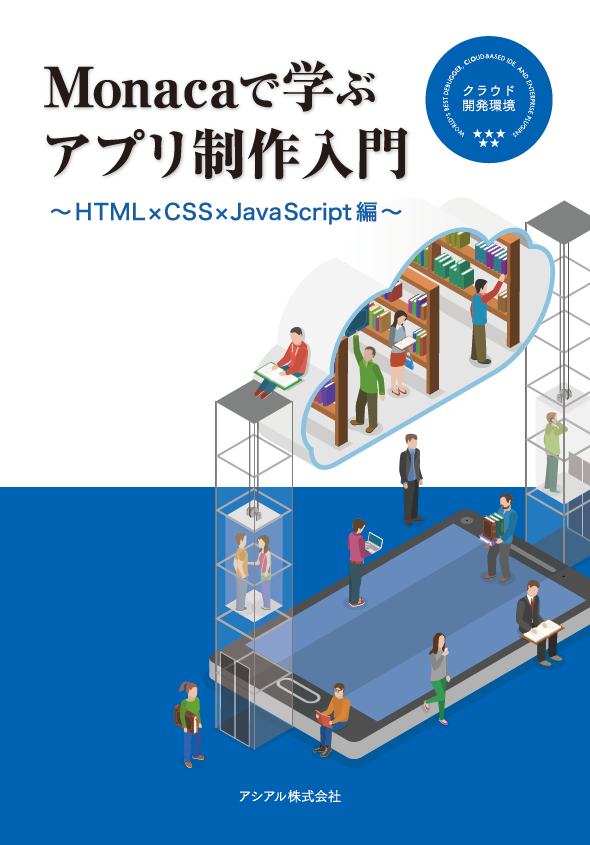
Monacaの教科書「Monacaで学ぶアプリ制作入門」
「Monaca Education」のメリットは何でしょうか?
岡田教諭:自分のスマートフォンで簡単に実際のアプリが動くというのが最大の魅力です。誰でもすぐに開発を始められる手軽さと、Web公開機能ですぐにスマホで動かせるというのは「Monaca Education」だから実現できたことです。
生徒のみなさんは「Monaca Education」を使ってみていかがでしたか?
黒澤さん:Web公開機能は本当に便利だなと思います。僕たちは物理部で子ども向けの英語学習アプリを開発し、プロトタイプを使って学童でユーザーテストを行なったんですが、その時にもすぐにiPadで動かせてとても助かりました。
森田さん:僕はC#(シーシャープ:Microsoft社開発のプログラミング言語)などもよく使うのですが、アプリのデプロイ(開発環境で作ったプログラムを一般に公開する環境へと移行する作業)でエラーが出ると解決に非常に時間がかかります。「Monaca Education」はそこがゼロなので非常に手軽です。開発画面でUI(ユーザーインタフェイス)を確認できるのも便利です。
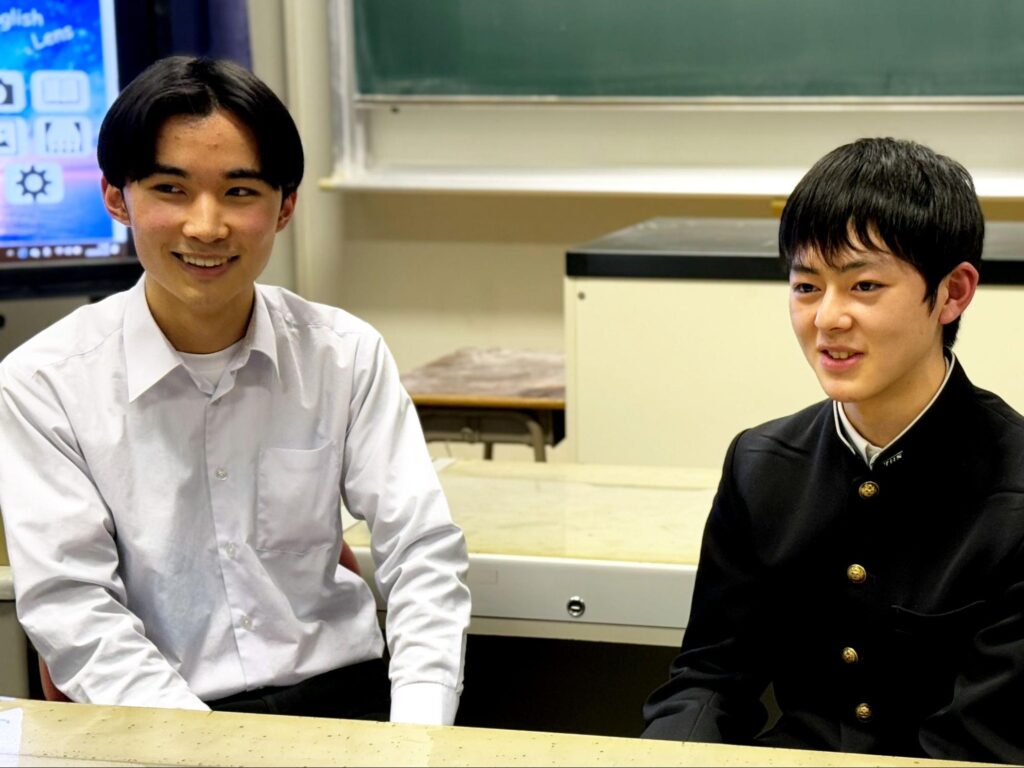
高崎高校3年生 左:森田大智さん、右:黒澤駿さん
お二人は授業では何を作ったんですか?
黒澤さん:一番最初は、ドキュメントの文字数カウンターを作りました。通常のサイトにあるのはリアルタイムでは無いので、リアルタイムにカウントできるものにしました。
森田さん:僕は単語帳を作りました。CSV(カンマ区切りのテキスト)ファイルでインポートができるように工夫しました。
探究では体系的に教えないことが重要
先生からご覧になって生徒さんの成長はありましたか?
岡田教諭:すごくできる子もいるし、難しいと感じている子もいます。探究では「ツールを紹介するけれど体系的には教えない」という方針です。ガチガチに組んだ体系的なカリキュラムを全員に教えて、それを使って、自分なりに少しアレンジするのは「活用」にすぎず、「探究」ではないと考えるからです。
「Monaca Education」などのツールは紹介しますが、「課題解決に必要な知識・技能は自ら習得する」「高校生の枠にとらわれず、使えるものは何でも使う」といったマインドで探究してほしいと考えています。
全員がすべてのことを同じようにできるようになってほしいわけではありません。探究学習では、一部の刺さる生徒が飛びぬけてできるようになる一方で、あまりできない生徒もいるのが普通なのではないかと思います。例えば、アプリ開発やプログラミングがあまり得意でない生徒であっても、それを経験することで新たな着想につながったり、グループでのアイデア出しに貢献できたりします。
探究を通して様々なツールや情報に触れる中でそれぞれの生徒が何か刺さるものを見つけ、それを深めていったり、自分の好きや得意を生かしてグループに貢献したりすればと思います。
体系的に教えないというところをもう少し聞かせてください。
岡田教諭:基本的に年間のスケジュールの中で、いくつかの発表会があって、それらがマイルストーンになっています。決まっているのは発表会の日だけです。前期は主にアイデア出しに注力し、後期では開発を行います。解決したいテーマが近い生徒どうしで自由に3、4名のグループになって取り組みます。1人で挑戦しても構いません。
生徒の自主性に任せていますね。先生がご苦労されている点があれば教えてください。
岡田教諭:難しいのは、特にデバッグ(プログラムの不具合を見つけ修正する作業)です。生徒がなかなか解決できずに手詰まりになってしまうこともあります。HTMLやCSS(Webページの内容やデザインを指定する言語)が複数ページにわたるとChatGPTで調べたコードをそのまま貼っても解決が困難なことが多いので、来年度は少しシンプルな雛形を用意できないかと考えています。
今年度は、地元企業の協力でUIの作り方のハンズオン授業を実施したり、生徒が作りたいUIの雛形をサンプルとして作ってもらったりして対応しました。
コンテストへ挑戦する意義とは
高崎高校では、国際学生科学技術フェア(ISEF)、ヨーロッパならびにアジア物理オリンピック、日本学生科学賞、中高生情報学研究コンテスト、Q-1 ~U-18が未来を変える★研究発表 SHOW~(以下、Q-1)、全国SSH生徒研究発表会、ぐんまプログラミングアワードなど、非常に多くのコンテストや発表会に挑戦し、数々の輝かしい成績をあげています。
コンテストへの挑戦の狙いを教えてください。
岡田教諭:大会は、目標の1つです。結果がどうであれ、力が伸びればOKですし、受賞すればモチベーションが大きく上がります。また、大会には〆切の役割もあります。人間は〆切がないとなかなか動けないものですから。

物理部で挑んだ「Q-1」の授賞の様子(左から 高崎高校物理部3年生 黒澤駿さん、細田晃祐さん、常見健太さん、森田大智さん)
物理部でコンテストに挑戦してみていかがでしたか?
黒澤さん:僕は高校生になって初めてプログラミングを始めたので、1年生の最初は、どちらかというと渋々参加していました。ただ、取り組む中でどんどんのめり込み、モチベーションが上がりました。今では主体的に参加しています。
森田さん:僕は比較的なだらかにチームに合流しました。大会も特別な意識なく取り組めました。
(取り組みの詳細は「アシアルnote 高校生の挑戦を支える、Monaca Education」をぜひご覧ください。)

「EnglishLens」画面(左 :起動画面、中央:撮影と翻訳の様子、右:翻訳画面)
コンテストへの挑戦では、先生はどのように関わったのでしょうか?
岡田教諭:技術的にはあまり指導しませんでした。プレゼンのロジックを組み立てるところをアドバイスしました。生徒たちは何度もプレゼン練習を行なっていて、ダメ出しをしあい、まるでケンカのように激論を闘わせていましたね。時間をかけて突き詰めていく体験が重要なのでアドバイスをしながら見守りました。
大会に向けて多くの時間を割いて取り組むのですが、勉強など他のこともしなければなりませんから、やりたいことがあるなら「自分のキャパを広げて、両方100%で頑張ろう!」という指導をしました。
理想的な探究とは/「Monaca Education」ができること
あらためて理想の探究授業について聞かせてください。
岡田教諭:自分の手で、「Monaca Education」で何かを作れると楽しいものです。そうするとプログラムが動く背景や、こういう風に作れるんだな、という理解につながります。体系的できちんとした「情報Ⅰ」教材が各社から出ていますが、そういった固定されたカリキュラムの通りに進めすぎると、そこにたどりつけないんです。
全員がプロのエンジニアや研究者になるのであれば、二進数など0から体系的に教え込むのも有効なのかもしれませんが、探究の目的はそうではありません。知識からではなく、もっと上流工程から入り、「楽しい」と感じることが最も重要です。そこで興味を持った子は、自ら体系的な知識を吸収していくはずです。
大切にしていることはどういったことですか?その中で「Monaca Education」の役割とは?
岡田教諭:子どもたちにじっくり考えたり、没頭したりする時間をあげること。「ゆだねる」「まかせる」を大切にしています。もちろん、ゆだねるだけでなくフィードバックやナビゲーションといった教員の適切な関わりが重要です。体系的ではない学びの中から、「興味」と「学び」の良い循環が生まれるのです。
そういったことを実現するために「Monaca Education」の造りが有効です。体系的に固定されず、自由に手軽にアプリを作れる点、生徒の「あったらいい」を形にするツールとして理想です。
探究では、アイデアを形にすることが大事で、プロトタイプと改善を繰り返すプロセスに重要な学びがあるので、「Monaca Education」が大きな役割を担っています。
最後に、学ぶ生徒たちへのメッセージをお願いします。
岡田教諭:「面白そう」「やりたい」を形にする上で、情報やプログラミングといったツールは有効です。少し前は、そういったツールの利用にはハードルがありましたが、今は個人のレベルでもできるくらい手軽になり、環境に恵まれています。
生徒たちには、「やってみたい」「便利にしたい」といった気持ちを突き詰めて考えて、世の中にないサービスや商品を生み出してほしいと期待しています。
岡田先生、黒澤さん、森田さん、本日はありがとうございました。
アシアルは、「Monaca Education」をはじめとするプログラミング教育環境を通じて、これからも中高生の学びと未来の実現を全力で支援してゆきます。
群馬県立高崎高等学校教諭。SSH部長、物理部顧問、物理担当。教員歴17年、同校赴任4年目。生徒たちが「Q-1」を始め、様々なコンテストへ挑戦する際には、共に伴走し、主体的な学びを通した成長をサポートする。
